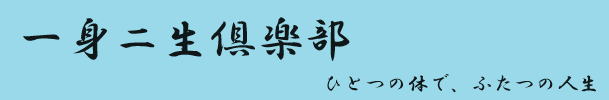産金国は鉱山から直接購入を始めた
この世界をつくった造物主がいたとすれば、その神様は「へそ曲がり」なのかもしれません。乾ききったアラビアの沙漠や、氷で閉ざされたシベリアの極地などに巨大な油田を配置し、貧しいアフリカや中南米の国々には地下に金や銀などの鉱脈をしのばせました。
これらの資源の多くは、欧米がいちはやく手をつけ、巨大企業が開発して利益のほとんどを持ち去りました。しかし、第2次世界大戦後、資源国が独立し、油田や鉱山を国有化したり、採掘企業に出資したりして、自国の権益を守るようになりました。
この流れはさらに進み、産金国の中央銀行は最近になって、準備資産の金塊を調達する方法を変え始めました。以前のようにロンドンなどの市場から買うのではなく、自国の鉱山から産出された金を直接買い上げるようになったのです。
世界金協会(WGC)の調査によると、この数年、自国の鉱山から直接金を購入する中央銀行が増え続け、昨年は14か国にのぼりました。それが今年の調査ではさらに増えて、19か国になりました。WGCは「金価格の高騰がこの動きを後押ししている」といっています。

アフリカのガーナ、タンザニア、中南米のコロンビア、エクアドル、アジアではモンゴル、フィリピンなどが自国の鉱山からの直接購入に踏み切りました。簡単なことのように思えますが、産金国には欧米資本の巨大鉱山会社のほかに、伝統的な手堀りで生活している人や、地元資本の零細鉱山があり、そこから直接購入するには事前の準備が必要でした。
たとえばタンザニア政府は、すべての採掘業者や輸出業者と協議を重ね、生産量の20%以上を中央銀行に売却することを義務付けました。購入価格は、地元業者にとって以前の売り値より高くする必要があります。しかし、中央銀行にとっても、ロンドン市場で購入してタンザニアに運ぶ輸送費や手数料が不要になるので、双方がトクをする価格は見つけられます。
この直接購入はには少なくとも3つの利点があります。第一に、手掘りの労働者や地元の零細鉱山にとって、信頼できる買い手が存在し、合法的で公正な方法で金を販売できるので、以前より安心して仕事ができるようになりました。
第二に、鉱山や手掘りの現場は多くが治安の悪い遠隔地にあり、犯罪組織がかかわり、ピンハネするケースが少なくありませんでした。しかし、直接購入によって政府の監督が強化され、犯罪組織を遠ざけることが可能になりました。
第三は、ロンドンで購入するには貴重な外貨を使っていましたが、直接購入は自国通貨で支払うので、外貨を減らすことはありません。金を購入した分、そっくり外貨準備資産が増えるので、自国通貨は強くなります。
問題は、中央銀行が買った金塊が世界で価値を認められるには、純度や重さなどの品質が市場で認定される必要があることです。ロンドン市場の規格は「純度99.5%以上」で、重さや純度、認定精錬業者などの刻印が求められます。

かつてはスイスの精錬業者がほぼ一手に引き受けていましたが、いまではフィリピン、カザフスタン、インドネシア、湾岸のドバイなどにも認定精錬所があり、委託先は広がっています。
WGCの最新調査では、中央銀行の95%が「世界の中央銀行は来年、さらに金準備を増やす」と予想しており、産金国の「国内調達」は今後も広がるでしょう。
そして、その先には、「金取り引きの覇権をどの国が握るか」「脱ドルが進んだ後に、国際貿易の決済をどうするか」という、世界経済を揺るがすような大きな物語が待ち構えています。それについては次号で書くことにします。(写真は Kizito Makoye/IPS、ブルームバーグ、サイト管理人・清水建宇 )