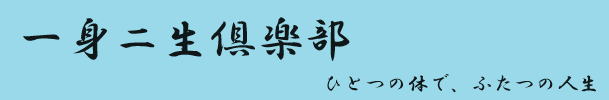イラン「金融核爆弾」の引き金
「金融工学」という言葉をご存じですか。コンピューター科学、確率論、金融経済学、会計学などと接点を保ちながら、急速な発展を遂げた学問です。1970年代には、マイロン・ショールズとフィッシャー・ブラック両氏が、確立微分方程式などを使った方程式を発表し、二人はこの業績で、のちにノーベル経済学賞を受賞しました。
受賞の2年後、ショールズ氏らが経営陣に名を連ねた巨大ヘッジファンドのLTCMは破綻しました。損失額は空前の規模になり、米国の連邦準備制度理事会が救済のために大手銀行の仲介に乗り出す騒ぎでした。ノーベル賞もたいしたことがないな、と言われました。
とはいえ、それで怖気づくようでは、カネもうけはできません。金融工学を駆使した新しい商品は、その後も欧米を中心に爆発的に増え続けました。総称して「デリバティブ(金融派生商品)」と呼ばれています。
たとえば、ある商品が一定の金額以上に値上がりしたり、値下がりしたりすれば、多額の利益が出るように設計された仕組み債などです。10倍、20倍などのレバレッジ(梃子)を利かせれば、わずかな投資で大きなリターンが得られます。
それぞれの「目論見書」には細かい説明が書かれていますが、高等数学がわからないと理解できません。金融業界には経済学部や法学部などの文科系が多いので、「35歳を過ぎたらデリバティブは無理」といわれているそうです。
こういう難解きわまる金融商品が、それこそ雨後のタケノコのように氾濫しましたが、どの国の政府も監督機関も、実体を正確につかむことができません。27年前ですら、たったひとつのヘッジファンドLTCMが破綻しただけで、米国の連邦制度理事会が乗り出すほどの騒ぎだったことを思うと、現在ではどれほどの衝撃を与えるのか、考えるだけで恐ろしくなります。
世界の投資家から尊敬を集めているウォーレン・バフェット氏は、2013年から「デリバティブは金融システムにおける大量破壊兵器、核爆弾だ」と警鐘を鳴らしてきました。世界の大手銀行に対しても「50行のうち(デリバティブに関わっている)45行は、投資先として検討にも値しない」と言い切りました。
さて、ここからイランの話に移ります。地図にあるように、世界の10大石油生産国のうち5か国がペルシャ湾に面しています。出口のホルムズ海峡は世界市場への唯一の出口であり、上下2本の航行レーンが設けられています。

航行レーンの幅は、わずか3km。米国のエネルギー情報局によると、世界の生産量の20%にあたる2000万バレルの石油が毎日通過しており、さらに世界のLNG(液化天然ガス)の輸出量の20%も、この海峡を通っています。
封鎖するのは簡単です。老朽した大型貨物船を航行レーンに沈没させればいいのです。米国自慢の空母群が駆けつけても、イランの陸地から集中的なミサイル攻撃を受ける恐れがあるので、撤退するか全滅するか、2つの選択肢があるだけです。
ホルムズ海峡の封鎖は、中近東で武力衝突が起こるたびに話題になってきましたが、これまで経済専門家の関心は、もっぱら石油に向けられてきました。石油の価格上昇が世界経済に打撃を与えるからです。
1973年の第1次石油ショックでは供給量の9%が失われ、石油価格は約4倍に上がりました。1979年の第2次石油ショックでは供給量の6%が失われ、石油価格は約3倍に上がりました。1990年のイラクによるクウェート侵攻では供給量の7%が失われ、石油価格は2倍以上に上がりました。
もしも今、海峡が封鎖されれば、供給の20%が失われ、石油価格は1バレル275ドルを超えるという試算結果があります。4倍以上に上がるわけです。
しかし、問題は石油価格ではないとの指摘が、最近、なされるようになりました。経済評論家のニック・ジャンプルーノ氏は、原油に連動するデリバティブが大量に発行されており、どれも「1バレル275ドル」などを想定していないので、破綻ラッシュになると警告しています。
「この破綻ラッシュは、デリバティブを保有する銀行や金融機関に、追加の証拠金(マージンコール)要求や強制的な売却の嵐を巻き起こし、バフェット氏が指摘したドミノ倒しの連鎖反応が発生するだろう」と言います。金融恐慌が起きるというのです。
イランが海峡を封鎖する可能性は、いまのところ、ごくわずかでしょう。トランプ米大統領は10発以上のバンカー・バスター爆弾をイランのウラン濃縮施設に投下しましたが、「もう核開発はできなくなった、終わりだ」と言って、手を引きました。イランは米軍基地にミサイルを発射しましたが、予告付きで、形だけの「反撃」でした。これを見て、石油の先物価格はほとんど動きませんでした。「海峡封鎖はない」と判断したからです。
しかし、イスラエルのネタニヤフ政権内では、超保守派の閣僚が「イランを殲滅せよ」と叫んでおり、米国にも「もう一度やれ」と主張する議員がいます。イランにも徹底抗戦を求める武闘派がいます。予測することは不可能だが、起きれば甚大な被害をもたらすリスクを「ブラック・スワン(黒い白鳥)」と言います。イランの「黒い白鳥」はまだ消えてはいません。(イラストはナショナルジオグラフィック、サイト管理人・清水建宇)