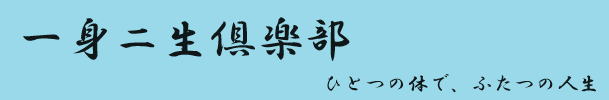準備金を本国へ取り戻せ!
欧州のバルカン半島の付け根に、セルビアという国があります。北海道よりやや広い国土に約700万人が住んでいます。かつては近隣を含めたユーゴスラビアの中核国でしたが、ユーゴが崩壊し、自治州のコソボとの対立をめぐってNATO軍の爆撃を受け、弱体化しました。
欧州連合への加盟を望んでいますが、NATOへの国民感情を考慮してロシアへの経済制裁には加わりません。一方でウクライナへの武器輸出の「う回路」を引き受けるなど、綱渡りの外交を続けています。そういう国の中央銀行が、準備資産として金の購入に力を入れたうえ、7月、「保有する金はすべてセルビアに送還し、国内で保管する」と宣言しました。

セルビア国立銀行が保有する金塊は50.5トン(約60億ドル)です。昨年は3.2トン、今年もすでに2.3トンと、購入ペースを上げてきました。その金を、すべて首都ベオグラードの保管庫に集める計画です。移送が完了すると、セルビアは東欧諸国ですべての準備金を国内で管理する初めての国になります。
多くの中央銀行が保有する金塊をニューヨークやロンドンに預けるのは、売却や貸し付けなどの取引に便利だからです。しかし、セルビア中央銀行は「取り引きの便利さと、国内保管の安全性を比較検討した結果、安全性を重視した」と述べました。
ウクライナ戦争の終わりは見えず、パレスチナ、シリア、イランでも戦火が続いています。トランプ大統領の関税攻撃は世界の経済を混乱に落とし入れました。セルビアの経済と独自通貨「ディナール」を守るには、金塊を手元に置いておかねばならない、というわけです。
セルビアだけではありません。インドは23年、24年と続けて100トンの金を本国へ送還しました。ハンガリーとルーマニアも本国送還の取り組みを始めました。前々回のこの欄で、「金準備が欧州中央銀行を上回った」と紹介したポーランドも、ほとんどを国内で保管しています。
6月24日、英紙フィナンシャル・タイムズは「ドイツとイタリアで、ニューヨーク連銀に預けている金準備を取り戻せという圧力が高まっている」と報じました。世界の金準備ランキングにおいて、ドイツは第2位の3352トン、イタリアは第3位の2452トンを保有する「金大国」です。
報道によると、ドイツとイタリアは、それぞれの保有量の3分の1以上をニューヨーク連銀に預けており、その市場価格は2450億ドル(約35兆5000億円)にのぼります。しかし、欧州納税者協会は、ドイツとイタリアの財務省あての書簡で「我われは金を本国に持ち帰ることを推奨する」と訴えました。この提言に政治家たちも同調し、「外国に預けるリスクを考えよう」などと発言し、世論も高まっています。
もともと、世界の主な中央銀行が準備資産の金塊をニューヨーク連銀やロンドンのイングランド銀行に預けるようになったのは、米国とソ連の「冷戦」が続いた時期に、共産圏から遠く離れた米英に預けるほうが安全だと考えたからだと、金の専門家は言います。

しかし、1989年にベルリンの壁が崩壊し、1991年にソビエト連邦が解体して、冷戦は終わりました。西側の欧米諸国が勝ち、東の共産圏は脅威でなくなりました。
それから30年余。ロシアがウクライナに侵攻すると、欧米はロシア中央銀行がニューヨークやブリュッセルに預けていた3000億ドルの準備資産を凍結しました。米ドルを経済制裁の武器として使ったのです。多くの中央銀行が、この制裁に驚きました。
準備資産を欧米に預けていると、凍結されたり、没収されたりする危険性があることが、はっきりしたからです。準備資産の中心だった米国債を売り、金塊を買う動きが広がりました。2021年から中央銀行は金を「爆買い」し始め、年間の購入量は1000トンに倍増し、その勢いは今年も続いています。
金の「爆買い」の次が、金の「本国移送」というわけです。
歴史を振り返ると、冷戦が終わり、米国の一極支配のもとで「パックス・アメリカーナ」と呼ばれた安定期が続きました。しかし、それも終わりつつあるのかもしれません。金の本国移送は、世界が新たな緊張に身構え始めたことを示しているようです。(画像はmoney metals、NY連銀HP、サイト管理人・清水建宇)