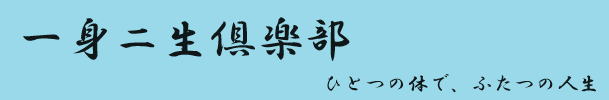鉛で金をつくった!?
人類が金を利用し始めたのは5000年前と言われています。古代エジプトの遺跡に「金」の記述があります。最古の貨幣とされるエレクトロン金貨がつくられたのは2700年前でした。数千年に及ぶ金へのあこがれは、やがて他の物を金に変えたいという願望となり、世界の各地に「錬金術」が広がりました。
とりわけ中世のアラビアで盛んになり、その文献がラテン語に翻訳されると、ヨーロッパでもさまざまな試みが行われるようになりました。下の図は16世紀の錬金術師たちの工房です。文献を調べる人や、何かを混ぜている人が描かれています。

しかし、他の物質を金にすることは、だれもできませんでした。それでも、試みの過程で、塩酸、硫酸などの化学薬品が発見され、実験器具も進化しました。錬金術は「化学(ケミ)」の語源とされています。その後、錬金術は歴史のなかに埋もれていましたが、今年になって、ニュースが相次いで流れました。
ひとつは、米国の経済学者ピーター・アール氏のレポートです。彼によると、スイスにある大型ハドロン衝突型加速器の中で、鉛の原子を光速に近い速度で衝突させたところ、金と同じ数の陽子を持つ原子が生まれました。つまり、鉛が金になったということです。ただし、金と同じ陽子数の原子は、100万分の1秒間しか続かず、すぐ崩壊しました。「錬金術師が夢見た、鉛から金への実用的な変換とはほど遠い結果だ」と結んでいます。
もう一つは、7月23日付けの日経新聞が報じた「米新興企業が錬金術を発見か」という記事です。これによると、米国で核融合発電の開発を手がける新興企業のマラソン・フュージョン社は、「核融合反応で生じる高エネルギーの中性子を使い、水銀の原子核の中性子の数を変化させることで金が生じる」という論文を発表しました。
この論文では、出力100万kwの核融合発電で、水銀から年間5000kgの金を生み出せるとしています。現在の価格で6億4000万ドル(約960億円)。「発電事業の収益が倍増する」と書かれています。
ただし、どの専門誌に発表したのか分かりません。科学論文に欠かせない専門家の査読も受けていません。核融合発電そのものが「夢の技術」で、米英は「2040年代の実用化」を目標にしており、20年も先の遠い未来の話です。眉にツバをつけたほうが良さそうです。
現代科学は、逆に「金を破壊できるか」という問題にも取り組んでいます。多くの金属は融点の3倍までしか過熱できず、これを超えると結晶構造が不安定になり、壊れてしまいます。科学誌ネーチャーが7月に載せた論文によると、米国のSLAC国立加速器研究所は、金を超高温にして、壊れるかどうかを確かめる実験をしました。

科学者たちは、レーザーを使い、金の融点1064度Cの3倍をはるかに超える高温まで過熱を続けました。金は融点の14倍以上の1万5000度Cを上回る高温に達しましたが、結晶は壊れませんでした。この実験で物理学の常識が覆され、「金は過熱限界がない可能性がある」という結論になりました。
他の物質で金をつくることはできない。金を破壊することもできない。――人類が昔から「貴重なもの」として扱ってきた金には、特別な性質があるようです。(図は浜松科学館、写真はslac national accelerator laboratory、サイト管理人・清水建宇)