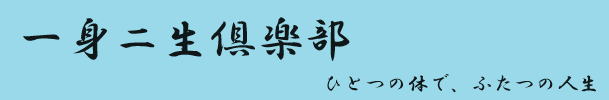金は買われすぎですか?
10月10日の金曜日、ロンドンの金現物市場は、1オンス(31g)=4018ドルで取引を終えました。金額も驚異的ですが、人びとをもっと驚かせたのは上昇のスピードです。

1971年、米国のニクソン大統領がドルと金の兌換を停止してから、金の公定価格は存在しなくなり、価格は市場で決まるようになりました。それから1オンス=1000ドルに達するまで37年かかりました。2000ドルに達したのは、それから8年後の2020年でした。
さらに1000ドル上乗せして、1オンス=3000ドルになったのは、5年後の今年3月14日です。つまり、1000ドル上昇するのに、37年、8年、5年と、それなりの年月をかけてきたのです。ところが4000ドルを超えるには、わずか200日しかかかりませんでした。6カ月余りです。
この異常な上昇ぶりに、欧米の金融界では「金は買われすぎだ」「いや、まだ上昇する」などと、熱い議論が続いています。それも当然です。今年の金価格の上昇率は、株式、ビットコイン、不動産などを引き離し、ぶっちぎりで1位を独走しているのですから。
「買われすぎだ」という主張は、株式市場などでおなじみの「ケイ線」分析が根拠です。一定期間内の上げ幅の合計を、下げ幅の合計で割って得た数値を「Relative Strength Index(相対力指数)」と呼び、70以上は「買われすぎ」を示します。10月上旬の金の指数は、なんと90.5に達しました。「きわめて買われすぎ」の状態です。
「まだ上昇する」という声を聞いてみましょう。その一人、クリス・パウエル氏は、西側諸国と銀行による長年の金不正取引を批判してきた、米国の組織「GATA」の設立者です。下のグラフが示すように、米国は2000年、欧州などの中央銀行に「金はもう不要だ」と働きかけ、14か国の中央銀行とともに年間400トン以下の金塊を売却する合意を取り付けました。この合意はさらに5年間延長されました。

中央銀行は2010年から再び準備資産として金を購入し始めますが、今度はニューヨークの金先物市場を舞台に、大量の先物を売り浴びせて金価格を押し下げる不正取り引きが横行します。FBIの捜査で、8年間に5万件の違法な取引があったことが分かり、2019年に銀行幹部らを起訴しました。GATAが指摘した通りでした。だから、クリス氏は「金は50年間、売られすぎだったのだ」と言います。
金市場の分析家であるマイク・マハリー氏は、別の観点から「買われすぎ」を否定します。金の市場ではアジアだけで5割を占めていますが、米国では長い間、金への関心が薄く、この数年の金上昇に対しても「傍観者」のままでした。ところが、いま劇的に変ろうとしていると指摘します。

米国では長い間「株式に60%、国債などの債券に40%」を振り向けるのが鉄則とされてきました。好況の時は株式が上がり、不況になると債券が上がって、補い合う関係にあるからです。金は枠外で、変わり者が買うだけでした。
しかし、大手のモルガン・スタンレー銀行の最高投資責任者であるマイケル・ウイルソン氏はこの秋、「国債よりも金こそがインフレの備えになる」として、「株式60%、債券20%、金20%」に配分し直すことを考えるべきだと発表しました。「60:40」ではなく、「60:20:20」が投資の新しい鉄則というわけです。
米国の投資資金は巨額です。天文学的な資産を持つ大富豪はもちろんのこと、勤労者も「401K」と呼ばれる自分の確定拠出年金口座で株式や債券に投資しています。その1%が金に振り向けられるだけで、膨大な金需要が生まれるでしょう。もしも20%が金の購入に使われると、たいへんなことになると、マハリー氏は言います。
こうした変化は、他の大手銀行も認識しています。ゴールドマン・サックスは10月6日、来年の金価格予想を1オンス=4900ドルに引き上げました。それまでの予想に600ドル上乗せしたのです。理由として、「中央銀行からの構造的な需要の強さと、FRBの金融緩和」を挙げました。利息がつかない金は、政策金利が下がると、買われやすくなるのです。
世界最大の金ETF(上場投資信託)を発行するSPDRゴールド・シェアーズは9月19日、1日の量としては過去最大となる18.9トンの金を仕入れました。ETFへの資金流入はずっと低調でしたが、ここ数カ月で急増し、9月だけで173億ドルも投じられました。
金を冷ややかな目で見てきた米国は、遅まきながら金市場に参入しようとしています。「買われすぎではない」と判断しているからでしょう。(グラフはREFINITIV、SBI証券、イラストはMoney metals、サイト管理人・清水建宇)