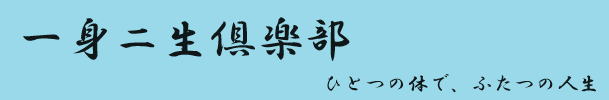金の値動きが荒くなった理由は?
今週のロンドン市場で、現物の金は1オンス(約31g)=4002ドル近辺で取引を終えました。下のグラフは、今年8月から10月末までの3か月間の日々の値動きを示したものです。値幅を示す「棒」は、形が似ているので「ローソク足」と呼ばれています。
長方形の棒の上端と下端は、それぞれ「始まり値」と「終わり値」を示します。上に出た線は「上ヒゲ」と呼ばれ、その日の最高値を示します。下に出た線は「下ヒゲ」と呼ばれ、その日の最安値を示します。つまり上ヒゲの先端から下ヒゲの先端までを見ると、その日の値幅が分かります。

この「ローソク足」は、1930年代に日本で考案されたものですが、いまや投資の最も重要なチャート、分析の道具として、世界中の金融機関や投資家が使っています。――ということを念頭に置いて、もう一度グラフを見てください。
8月から9月中旬まで、つまり1オンス=3600ドルあたりまでは、一日の値幅が小さかったのに、その後は値幅が急に大きくなったことが見て取れるでしょう。市場の用語でいうと「値動きが荒くなった」わけです。
世界の市場は東から西へと、順番に開いていきます。まずアジアが開き、次に欧州、最後に米国が開きます。私はこの2年あまり、金の値動きを眺めてきましたが、アジアでは金の需要が多いので値が上がり、米国では売り物が多いので値が下がるのが、多いパターンでした。その結果、一日の値幅は小さく、値動きも比較的なだらかだったのです。
ここにきて値動きが荒くなった原因のひとつは、投資用の金の需要が急増したことだと思います。ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC、世界金評議会)によると、今年7~9月の世界の金需要は史上最高となり、とりわけ投資目的の購入が前年同期の1.5倍に達しました。
投資目的の場合、金の上場投資信託(ETF)の形が多く、金需要の半分は欧米のファンドのETF向けです。そのため、米国市場が開いても金は値下がりせず、逆にETF向けに買われたりして、値動きのパターンが崩れました。米国市場が開くと、数時間のうちに値上がりと値下がりが繰り返される日も珍しくありません。

ETFは金価格と連動する「証書」に過ぎませんが、少額でも買えるうえ、株式と同じようにスマホやパソコンで簡単に売り買いできます。デイトレーダーと言われる人たちは、株価が下がれば「飛び乗り」で買い、上がれば「飛び降り」で売却を繰り返しますが、金ETFを買った人たちの多くも、利ザヤを得ることが目的で、売買を繰り返すのでしょう。
中国やインドなど、金を愛好する人が多いアジアでは、最後の拠りどころとして金現物を蓄える傾向が強く、売買を繰り返す人はわずかです。そこに、欧米流の利ザヤ稼ぎの取引が加わった結果、金の日々の値動きが荒くなったのではないでしょうか。
では、ETFの売買が増えた結果、現物の金価格が大きく下がるのか、その点は気になります。WGCは最近の金需要の急増について、「未知の領域に入った」と表現しました。これまでの経験で予測することは難しいということです。
とはいえ、世界の中央銀行の金買い意欲は衰えていません。韓国中央銀行の総裁は10月末、「準備資産として金の追加購入を検討中だ」と述べました。「金シフト」グループに加わる意向表明です。14億人余の人口を抱えるインドと中国でも、民間の金需要は高いままです。
もう一度、金の値動きのグラフを見てください。3本の線が描かれていますが、上から順に緑色が5日間の価格を平均した移動平均、赤色の線は25日間の移動平均、紫色の線は75日間の移動平均です。赤と紫は長期間のトレンド(趨勢)を表しています。これを見ると、右肩上がりは、まだ続きそうな感じです。(グラフはRifinitiv、イラストは台湾EBC、サイト管理人・清水建宇)